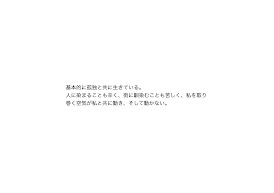Tokyo analog vo.16 より
このエッセイを東京アナログに寄稿したのは去年の7月のこと。
この1年で少しだけ心の持ちようが変わったことに気づく。
ただただ敵としか見ることのできなかった通り過ぎる人やビル群。
自分の為に必死に生きる、目線が足元の人々を慈悲と恐怖を覚えた。
異常とすら思った。
そしてその場所にいる自分も異常の一部いうダブルスタンダード。
このエッセイのラストでは、
「足場の悪いこの場所でこれからもなんとか生きていくことになるだろう」
「たとえ目が眩むようなビル群の間を流れる人々がただの駒に見えても」
と言っている。
我ながら凄い喧嘩の売り様。
「東京を好きになろう」「東京を好きにならなければ、東京の人には好かれない」
の言葉を掲げ自分なりに頑張ってはみたが、
出掛けるたび目眩や筋肉の強張りが続き、その後行動が伴わなかった。
腑に落ちない部分がある表れだと思う。
*
このエッセイから1年。
お仕事でふと出会った私より10近く年上の人と世間話をしていて、
「東京に染まりたくないし馴染みたくもない」とポロッと言ってしまった。
その方の返答は、
「表現者は染まらなくていいし、馴染まなくていい、寧ろそうなっちゃだめだ」
だった。
身バレ防止のためその後仰ってくれた理由は割愛するが、
スッと私の肚に落ちたその言葉に恐らく相当救われたんだろう。
半ば諦めの目でビル群の景観に慣れつつあった良くない足場から少しホバーした感覚。
*
もう少しモデル的目線で言うと、これは「新鮮さ」に関係している。(たぶん)
見る人が感じる新鮮さ。
経験を積めば積むだけ新鮮さは削がれ(これも良いこと)、自然に玄人さが醸し出される。
逆に経験があるのにいつ見ても「この人は新鮮だな」と感じさせられる人はだいぶ少ない。
トーキョーを表そうが、フレッシュを表そうが、はたまた別の何かを表そうが、どれでも大丈夫。
私は染まらず馴染まずの諦観者のまま、この場所でこれからもなんとか生きていくだろう。